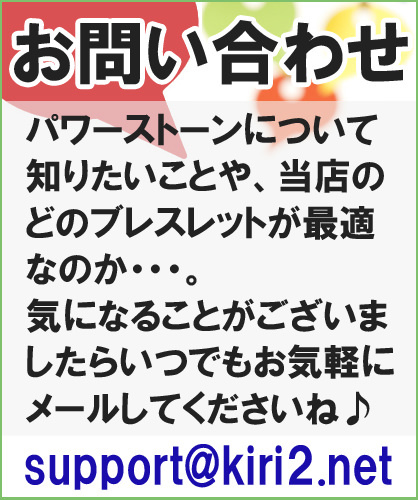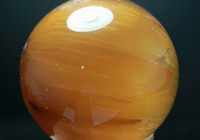パワーストーン (天然石)の写真の撮り方|カメラだけでOK

パワーストーンブレスレットなどを自作されておられる方で”販売”をされておられる方もいらっしゃると思います。
販売するために絶対に必要なのは写真ですね。
どのように撮影すればパワーストーン(天然石)の写真を美しく撮ることができるのでしょうか。
今回は当店が実際に行っている方法をそのままご紹介しようと思います♪
※撮影初心者の方が、”販売”するための写真をサイトに掲載することを想定しています
カメラだけでOK。その他の機材は一切必要ありません
撮影方法やテクニックなどをネットで調べるといろんな方法が紹介されています。
どれも素晴らしい方法・テクニックだと思いますが、正直・・・面倒です。
専用のライトやレフ板、極めつけは簡易スタジオなどなど。場所もとりますし、お金もかかります。
カメラだけあれば十分です。三脚すら必要ありません。
高性能のカメラである必要はありません。スマホに搭載されたカメラではなく、15,000~20,000円ほどのデジカメがオススメです。
太陽光で撮るのが基本中の基本
美しい写真を撮るには光が必要です。光が少ないとそもそもピントすら合いませんからね。
専門的なライティングは必要ありません。室内の蛍光灯での撮影は論外。必ず太陽光で撮影しましょう。
どんなにがんばってライティングしたとしても太陽光には勝てません。なぜなら、私たちが普段目にする光は太陽光なのですから。
プロ級の設備・テクニックでの撮影は信頼を失う可能性も・・・
素晴らしい写真は目を引きます。購買意欲が湧いてくるに違いありません。
しかし、あまりに美しく撮影されてしまうと「写真と現物のギャップ」が生じます。
要するに、サイトで見た写真に惹かれて買ったけれど、全然写真と違うじゃないか!というクレームに繋がる可能性があります。
クレームまで至らなくても「このお店ではもう買わないでおこう」と思われてしまうでしょう。信用を失ってしまったわけです。
写真だけで完結するなら美しければ美しいほど良いですが、現物を手にしてもらうのですから”リアリティ”がもっとも大切になってくるわけです。
撮影例1|たっぷりの太陽光で撮影

モリオンとラブラドライト、そして水晶とルチルクォーツさざ石を撮影しています。
太陽光がいっぱいの屋外で撮影しました。
いかがでしょうか?
撮影例2|晴れた日の”日陰”で撮影

撮影例1とまったく同じ時間に、場所だけ変えて撮影しました。
少し日陰になっている場所で撮影しています。
いかがでしょうか?
美味しそうに見える色合いを目指そう♪
上記の例で言えば、おそらく全員「例2」の方が良いと思ったはずです。
太陽光が多すぎると色が飛んでしまい、なんとも言えない残念な感じになってしまいます。本来の色とはまったく違う色で撮れてしまいます。
日陰だと色が飛ばず、本来の色にかなり近い色合いで撮れます。曇りの日に撮影すると最高です。
どちらが美味しそうに見えますか?
間違いなく「例2」ですよね。
パワーストーン(天然石)の撮影は「美味しそうに撮る」のが正解です!
最低限の調整(フォトショップなど)で完成させよう

こちらの写真は「例2」をフォトショップで少しだけ調整したものです。
フィルタのシャープをちょっとだけかけて全体をより鮮明にし、トーンカーブでほんの少しだけ全体を明るくハッキリさせました。
色彩などは一切手を加えていません。最低限の調整だけです。
いかがでしょうか?
かなり良い感じになったと思います。ほんの1分ほどの時間で調整したので、もう少し時間をかければもっと素敵になります。
太陽光で撮影し、フォトショップでの調整は最低限。限りなく現物に近い雰囲気・質感・色合いで、しかも美味しそうに仕上がりました。
専門的な機材を用いなくても十分ですよね。
ブログに掲載するために写真は小さいサイズにしましたが、縦横1000ピクセルを超える大きな画像であってもまったく問題ありません。
(そもそもデジカメで撮影したときの写真のサイズは縦横3000~4000ピクセルですからね)
せっかく素敵な作品をつくっているのに写真が残念な感じになっているケースが見受けられます。
当記事の内容は実際に当店が行っている方法です。専門的な知識や経験・機材など一切不要です。だれでも今すぐ美しい写真を撮ることができるはずです。
服やおもちゃなどの写真も同じ方法で美しく撮れるかは分かりません。経験がないので。
おそらくどんな対象物であっても問題なく美しい仕上がりになるとは思います♪
ぜひ参考にしてみてくださいね。
【注意】水晶玉で火事になる!?収れん火災に注意

ここ最近山火事に関するニュースがテレビから流れてくることが多いですね。
「大変だなぁ・・・」と人ごとに思ってしまいがちですが、いつ自分自身が火事に遭遇してしまうか分かりません。
”水晶と火事(収れん火災)”の話は有名ですが、一応当ブログでも取り上げておこうと思います。
水晶玉で火事になる可能性はゼロではありません
虫眼鏡で太陽光を一点に集めて火をおこす。小学生の頃に理科の実験で経験したことがあると思います。
これをまったく同じで、水晶玉が太陽光を一点に集めてしまい火事へと発展(収れん火災)する可能性はゼロではありません。
それほど頻繁に耳にすることはありませんが、日本はもちろん、海外でも水晶玉が原因で火事になってしまったという話は実際に存在しています。
テニスボールのサイズを基準にするとよいと思います
水晶玉をお持ちの方はどれくらいのサイズをお持ちでしょうか。
以前実験してみたことがあるのですが、その経験から申し上げるとテニスボースくらいのサイズがボーダーラインになると思います。
テニスボールくらいのサイズよりも大きい水晶玉だと火をおこす可能性はグッと高まります。小さいサイズだと逆にグッと低くなります。
あくまでも私の経験上の話ではありますが、実験してみた結果なのでそれなりに信憑性はあるだろうと思います。
水晶玉以外でも火をおこす可能性があります
言うまでもありませんが水晶以外でも火をおこす可能性があります。
”光を屈折させて一点に集める”ことで火をおこすわけですから、これができるモノであれば何であっても要注意ですね。
ガラス玉もそうですし、透明度が高い天然石や宝石もそうでしょう。
100円ライターや水を入れたペットボトルが収れん火災の原因になったりするケースもありました。
ちなみに、ねこを近づけないために水入りのペットボトルを置くのがブーム?になったことがありましたが、まったく根拠の無い話です。
今でもたまに見かけますが、収れん火災の原因になりかねないのでちょっとこわいですね。
夕方が危険な時間帯
意外?なことに、収れん火災が起こりやすいのは昼間ではなく夕方のようです。
理由は簡単で”室内に光が入りやすいから。また、その時間が長いから”です。
カーテンなどで太陽光を弱めよう
水晶玉に光を当てると美しいですよね。直射日光を当てるとおどろくほど力強い光に目を奪われてしまうと思います。
ですが”火事にならないようにする”ことが最優先ですので、普段は直射日光が当たらない場所に置くようにしてくださいね。
窓際に置く際は薄いカーテンで光を弱めてあげれば大丈夫です。強い直射日光が当たらない限り火をおこすことはありませんので。
窓際や車内に水晶玉など(光を集めるモノ)を置いてる方は注意してくださいね。
世界最大のブルーダイヤが競売大手クリスティーズに出品される

(c)AFP=時事/AFPBB News
クリスティーズ(Christie's)といえば世界的に知られるオークションハウス(競売会社)です。サザビーズがライバルですが、世界一の規模を誇るのはクリスティーズとのことです。
何億・何十億円といった驚くほどの価格が1枚の絵画につけられたりするわけですが、いったいどんな人が落札するんだろう、、、と興味をそそられますね。
そんなクリスティーズに世界最大のブルーダイヤ(13.22カラット)が2014年5月14日に出品されるということで注目を集めています。
当記事の画像はまさにそのブルーダイヤです。
動画で見る世界一のブルーダイヤ
国際ニュースといえばAFPBB Newsといった感じですが、AFPBB Newsのyoutubeチャンネルに噂のブルーダイヤの動画ありましたのでご紹介します。
美しさは言うまでもありませんが、これほどのブルーダイヤ。もし仮に手にしたとしても怖くて身につけれません(笑)
落札予想金額は2100万~2500万ドル(約21億円~約25億円)とのことですが、あまりに現実味がない数字なので割高なのか割安なのかまったく分かりませんね。
1カラット当たり価格の最高記録を更新するか!?
2013年、英競売大手ボナムズ(Bonhams)にブルーダイヤモンド(5.30カラット)をあしらった指輪が出品されたことがありました。
620万ポンド(約9億4600万円)で落札されました。単純計算で、1カラットあたり180万ドル(約1億7800万円)となります。※ポンドとドル表記が混在しています
どうやらこの「1カラットあたり180万ドル」が現在のところ最高額らしいのです。
今回の世界最大のブルーダイヤの落札予想金額は2100万~2500万ドルですから、1カラットあたりだと”159万ドル~189万ドル”となります。
1カラットあたり価格の最高記録を更新する可能性を秘めているわけですが、さて・・・どうなるか楽しみですね。
どのような結果になったかは、また当ブログでご紹介しますね。
簡単には切れない一生モノのパワーストーンブレスレットの特徴

パワーストーンブレスレットの品質は、中糸(紐)の品質が非常に重要なキーポイントとなります。
切れにくいのはもちろん、質感・安定感・安心感そして耐久性といった項目は中糸(紐)の品質がものをいいます。
関連記事
品質の良いパワーストーン・ブレスレットの見分け方
パワーストーンブレスレットの中糸に注目しよう
言葉ではなかなかうまく伝えにくい内容ですので、動画で実際にご覧いただこうと思います。
男性の力でも簡単に伸びない”強さ”
実際に当店のパワーストーンブレスレットを力いっぱい引っ張っている動画をご紹介します。
私の指が移っていますね(笑)男性である私がグググッと力を込めてがんばって引っ張っています。
引っ張った瞬間はムニッと伸びますが、次の瞬間からかなりの抵抗があることが見て取れるかな、と思います。
当店のパワーストーンブレスレットの中糸(紐)は”元の長さに戻ろうとする力”がとても強い特徴があります。そして、繋ぎ目がありませんので抜群の耐久性がございます。
この特徴により長年愛用してもブレスレットが伸びてしまうことはありません。
伸びてしまうと石と石の間に隙間ができてしまい不格好になるのと、石同士の衝突が激しくなるため欠けてしまう可能性も出てきます。
伸びないことはとても大切なわけです。
ブレスレットは「石」と「中糸(紐)」で出来ているわけですから、どちらの品質も重要であり、どちらにも自信を持てなければいけません。
変な例えになりますが、テレビで見るラーメン屋さんはみんな「スープが命!」と謳っていますが、ラーメンは麺もありますよね。
いくら素晴らしいスープであっても、麺がダメならラーメンとしては二流でしょう。この逆も然りですね。
ブレスレットも同じで、石の素晴らしさばかり謳うのは間違いです。それを繋ぐ中糸(紐)の素晴らしさを兼ね備えてこそ一流でしょう。
といっても…お店に並んでいるブレスレットをグッと引っ張る行為はよくないですが、ご安心ください。手にとった瞬間にだいたい分かるものですので。
ネットショップでお買い物される際は、中糸(紐)に関して十分な説明がなされているかどうか確認するようにすると良いと思いますよ。
天然石のモース硬度とは?|どのレベルまでが傷つきやすいのか

パワーストーン(天然石)を調べていると必ず登場するのが「硬度」です。正確には「モース硬度」です。
書いて字のごとく”硬さ”を数字で表現しているわけですが、少々誤解を招きやすい数字でもあるので詳しく説明しておきますね。
モース硬度は「頑丈さ」ではない
”硬さ”と聞いてどんなイメージをしますか?
硬ければ硬いほどハンマーで叩いても割れない!といった感じで頑丈なイメージを持つ方が圧倒的に多いと思います。
それではこれはどうでしょう。
庭で適当に拾った石と粘土があったとします。それぞれをハンマーで叩いたらどうなるでしょうか。
石は砕けてしまいそうですが、粘土は変形するだけで割れることはなさそうですよね。
硬いと衝撃に弱くなってしまうのです。
小学校の理科の実験で、鉄の”焼入れ”と”焼戻し”をしたことを思い出していただけると分かりやすいですね。
硬いと逆に粘りがなくなり、衝撃に弱くなってしまうわけです。
ですので、モース硬度が高いから衝撃に強くて丈夫というわけではなく、むしろ逆である場合が多いんです。
取り扱いには十分注意してくださいね。
そもそも”モース硬度”ってなに?
モース硬度とは1822年にドイツの鉱物学者フリードリヒ・モールスが考案した鉱物の硬度を表す基準です。
1~10まであって、数が多ければ”硬い”ことになります。
モース硬度10が最も硬い鉱物の称号となり、該当するのはもちろんダイヤモンドです。
鉱物同士を擦り合わせて、どっちが傷つくかを調べて数字を決めていきます。
傷ついた方の硬度は低く、傷つけた方の硬度が高いわけですね。
”衝撃に強いかどうか”ではないという点がポイントです。あくまでも擦り合わせたときどっちが傷つくかを見ているわけですからね。
また、前述したようにモース硬度は1~10だけしかないので、同じモース硬度5であったとしても同じ硬さとは言えません。
なんていうか、けっこう大雑把にざっくりと決められている感じですね。
モース硬度を分かりやすく置き換えてみると
モース硬度5!と聞いてもいまいちピンとこないですよね。
うーん、中間くらいの硬さ???って感じですが、具体的にどれくらいの硬さなのでしょう。
ばっちりイメージできるようにするには、ざっくりと覚えてしまえばよいと思います。
- モース硬度1:グッとつまむと変形するくらい
- モース硬度2:指の爪でがんばって傷つけれるくらい
- モース硬度3:硬貨などでなんとか傷つけれるくらい
- モース硬度4:ナイフで簡単に傷つけれるくらい
- モース硬度5:ナイフでなんとか傷つけれるくらい
- モース硬度7:ガラスや鉄鋼、銅が逆に傷つけられるくらい
ざっくりとした表現ですが、モース硬度3までが「ふと傷つけてしまうレベル」でしょう。
モース硬度5になるとナイフで意図的にがんばって傷つけようとガリガリしてやっと傷つけれるレベルです。
さて、ここで興味深いことに気づかれた方もいらっしゃるかもしれません。
モース硬度4と5の違いがハッキリしていますよね。4は”簡単に”なのに、5になっただけで”なんとか”と表現が変わります。
モース硬度が1つ違うだけでかなりの差があることが分かりますね。
ビッカース硬度で見る、モース硬度9と10の圧倒的な差
モース硬度9の次は10ですが、その差は驚くほど開いています。まったくの別物と言っても良いレベルです。
ビッカース硬度という”圧力にどれだけ強いか”を示す数字があるのですが、これをモース硬度ごとに当てはめてみると・・・
- モース硬度 = ビッカース硬度
- 1 = 50
- 2 = 60
- 3 = 140
- 4 = 200
- 5 = 650
- 6 = 700
- 7 = 1100
- 8 = 1650
- 9 = 2100
- 10 = 7000
詳しい説明は割愛しますが、モース硬度9から10になるだけでビッカース硬度は一気に跳ね上がっていますね。
いかにモース硬度10というのが圧倒的か分かります。さすがダイヤモンドといったところでしょうか。
今回はモース硬度に関して詳しく説明してみました。
普段はとくに硬度とか気にすることはないと思いますが、前述したように「モース硬度3までがふと傷つけてしまうレベル」とだけ覚えておくと便利だと思いますよ。